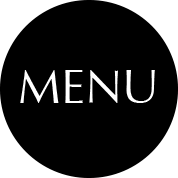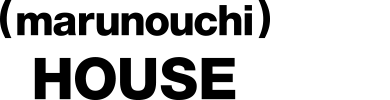Text_Viola Kimura
今回のゲストは、自身のブランドを立ち上げて22年目を迎えた丸山敬太氏。そのエンターテイメント性溢れる表現は国内にとどまらず世界の注目の的だ。コレクションはあらゆるカルチャーの美が融合した幻想的な世界観で、ディテールの細やかな心遣いや、まとうだけでハッピーになれそうな空気感には彼の人柄そのものが滲み出ている。そんな丸山氏は自身のコレクションを再びグローバルな舞台へ広げていく準備の最中だ。日本を代表するデザイナーである彼の目に、日本がどう映っているのか、話を聞いた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
![]()
丸の内ハウスへはイベント登壇でお越しいただいていますね。
「はい、毎年夏に開催されている“HOPE AND LOVE”などで何度か来ています。昨年は雨宮塔子さんと“パリのカフェトーク”というテーマでトークショーをさせていただいて。以前、大宮エリーさんともご一緒させていただきましたね」
2016年春夏コレクションはロマンティックなムードでとても素敵でした。丸山さんの表現のファンタジー性というのはどこから来るんでしょうか。日本的なモチーフが印象的ですが。
「自分の性質ですかね。ファッションっていうものへの入り口が、僕にとってはファンタジーだったので。ファッションというものを仕事に選んだ時点で、ファンタジー性があるかなと思います。アジアンティックなものとかオリエンタルなものはすごく好きなんですが、その理由はわからないです。前世とかじゃない? って思ってるんですけど(笑)。DNAのなかにあるんじゃないでしょうか。でも、いわゆる“日本的なもの”が何でも好きかと言われたら、必ずしもそうでもないんです。ミックスなんですよね。ちょっと横から日本を見て、きれいなところだけ拾った、みたいな、そういうものが好きなんですよ。骨董なんかでも惹かれるのは、日本から輸出用につくられて海外に出ていったものだったりして。いわゆる本当の侘び寂びといったものとか、あらゆる日本のものが好きかと言われたら、そうでもないんですよ」
今季でいうと陶器を思わせるブルーの小花柄が印象的でした。以前手がけていらした西陣織のドレスも素晴らしいですよね。
「ソフィスティケートという言葉が正しいかどうかわからないですけど、ツボに入るポイントというのが自分のなかにあって。いわゆる”日本的な”ものを、そこまで意識的に取り入れようとしているわけではないのですが、パリに行って挑戦し始めたころに、インターナショナルなフィールドで戦うならば、よりパーソナルになることが必要だと感じたんです。それはよりナショナルになり、そしてパーソナルになる、ということだと思ったので、自分のなかにあるそうしたものをもっと大事にしようとは思っています。特に最近は、日本でものをつくるということを意識しています」
アジアの顧客も増えているかと思いますが、国外での展開が広がって、どのようなことを感じますか。
「そうですね。色んな国がありますけど、日本という国がどれだけ特殊かっていうのは強く実感しています。こんなに国土が狭い国であれば外に出てお金を稼がないと成り立たないはずが、中で商売が生き残ってきた。中国を別にして、アジアに外向きの国が多いなか、日本はマーケティングが全て中に向かっていて、生産して消費するという仕組みが中でぐるぐる回っている。そんな特殊な、ある意味健全、ある意味不健全な状態が戦後長く続いています。それが壊れ始めたのがここ10年くらいの出来事ですよね。これからは日本もグローバル化してアジアに近くなっていくと思います」
日本人はもっと外を向いていくべきだとお考えでしょうか。
「それしかないでしょう。日本にエネルギーが溢れて、外の人たちを迎え入れて、もっとカルチャーがミックスされていったとき、日本人が本来持っているホスピタリティといったものが武器になる。難しいことを考えなくても、自分たちが日々やってきたことを形にするというだけで、差別化はできるんですよね。僕が初めてパリへ行ったとき、自分としてはそんなに日本というアイデンティティを意識していなかったのですが、コレクションを色々なプレスに見せて歩いていた際に、とても日本的なデザインするのね、と言われたんです。例えばタータンチェックのプリーツスカートをつくっていても、すごく日本的だと言われて、ああそっか、って。自分がもう既に、この人たちとは違うカルチャーをいきて育ってきているわけだから、自分の目を通して素直につくったものは、もう自分だけのものなんですよね。カルチャーがミックスされていくと、自分たちが持っているものに気づいていくはずなので、東京、日本がより面白くなっていくんじゃないかと思います」
“日本的”と言われるファッションのエッセンスは、アジアと欧米で見え方が違いますよね。
「全然違う。時代によっても違うし、人種によって由来が違いますから。やっぱり狩猟民族とは違う。狩猟民族の酒の飲み方と肉の食べ方は違うって思いますもん(笑)。生活の仕方、例えばセックスに対する考え方が違えば、セクシーの表現とかも違ってくる。そうすると洋服、つまり性的なものを匂わすか隠すかということ、あるいは防寒といった機能面のどちらから発祥したものを、どういうことで表現していくかっていうのはそれぞれのカルチャーで違ってくる。カルチャーだけでなくてパーソナルなところでも違うし。ところが本来は、パーソナルによって違うってことが面白さなんだと思うんですが、いまの日本の風潮は、どちらかというと個性を表現するのではなく、まわりに同調してしまう。同調したなかで出していくちょっとした細やかなところが日本文化の面白いところって言われれば、まあそうかもね、とも思いますが。でも僕はもうちょっとみんな自由でいいのに、と感じているんです。まだまだ僕らの若い頃は、真逆のテイストのファッションの人たちが親友だったりしましたから。でもいまって、友だちだったらユニット、つまり同質みたいなことになっちゃってるじゃないですか。それがちょっとつまんないな、と思います」